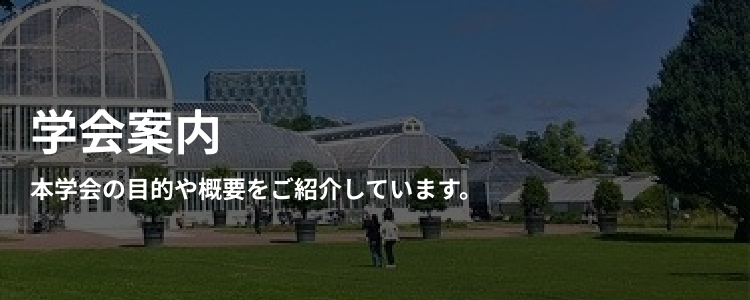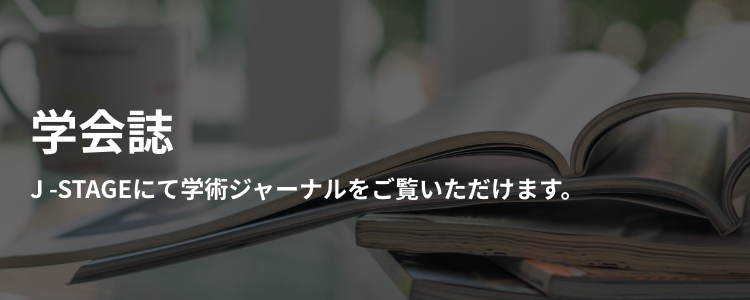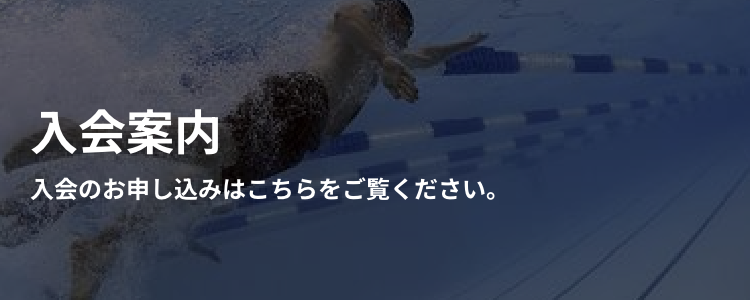日本水泳・水中運動学会第5代会長
慶應義塾大学
政策・メディア研究科兼環境情報学部
教授 仰木 裕嗣
2025年4月より日本水泳・水中運動学会第5代会長を拝命いたしました,仰木裕嗣と申します.就任にあたり,会員の皆様,ならびに水泳・水中運動に関心をもつ方々へのご挨拶をさせていただきたく存じます.
野村照夫前会長からのバトンを受け継ぎ水泳・水中運動に関わる幅広い研究を議論する場としての当学会が今後どのような方向へと向かうのか,会長として考える立場となったことに自分自身驚きを隠せません.日本水泳・水中運動学会会員の多くは水泳経験者,水辺活動の経験者が多いのは周知の事実ですが,私自身ももとは競泳選手であり,その後は競泳コーチでもあります.そんな一水泳選手,一水泳コーチであった自分自身が本学会に参画したのは学会発足当初ですが,四半世紀を経てよもや会長を務めることになろうとは思いもよりませんでした.
本学会会長就任を打診されて以来,今後の日本水泳・水中運動学会が向かう方向,日本の水泳にまつわる課題に対して本学会がどのように貢献できうるか考えを巡らせて参りました.
コロナウイルス禍を経た現在,日本の水泳を取り巻く環境は大きく変化しています.新聞報道でもご承知のとおり,学校教育現場における水泳授業の継続不可能といった話題です.理由としては施設の老朽化,教員の負担が挙げられています.施設の改築や教員の増員といった各自治体が予算措置を講じなければならない課題については,我々学術団体として手を差し伸べるは出来ません.しかしながら,水泳指導に関するこれまでの科学的・教育学的知見と経験,そして何より我々水泳研究者の人的ネットワークは教員の指導力強化という部分において必ずや貢献しうると考えています.全国的な課題となっている水泳授業にまつわる困難に対して我々,日本水泳・水中運動学会員も立ち上がるべきと考えています.
羊水の中で漂っていた我々ヒトは生後間も無く,泳ぐことが本能として可能です.しかしながら,その後は学ぶことで泳ぎを獲得します.水泳,水中運動は身体運動のなかで唯一,無段階・全方向負荷を与えることのできる運動であり,三次元的な動きをゆったりとした時間の流れのなかで経験できる運動でもあります.当学会初代会長の故宮下充正東京大学名誉教授が繰り返し仰っていたように,「水泳は0歳から100歳までは同じ環境で楽しめる唯一無二の運動」であります.この特異性・独自性が身体教育においてどのように活かされるかは,我々研究者のみならず学校体育指導者,民間水泳指導者らに委ねられていますが,より一層の科学的・教育学的な知見が普及することを願っています.
水泳研究者の多くが水泳競技経験者であったことから水泳研究の多くは競技志向になりがちですが,現代社会において多様なスポーツ・文化的活動が存在し,多くの他の楽しみがある中で,「泳ぐ」という行為に対する興味・関心が人々の心から離れていくのはやむを得ないかもしれません.人口減少の中では水泳志向人口も減っていくことは容易に想像できます.しかしながら,先述の泳ぐ行為,あるいは水中という特殊環境の持つ優位性や安全性をより科学的な見地から社会に訴えていくべきと考えます.「F1ビジネス」はF1で培った知見を大衆車に展開することを指しますが,アスリートを対象にしたトップレベルの水泳研究をより広く,幼児・児童から高齢者,障害者までにも転用するといった社会的貢献も学会員の研究者に大いに期待しています.
学術団体としての日本水泳・水中運動学会は2025年現在,会員数200名にも満たない小さな組織です.しかしながら,国際的に見れば日本には水泳研究者が非常に多いことも周知の事実であり,4年に一度開催される国際水泳医科学会議(Biomechanics and Medicine in Swimming)には,日本人研究者がその多くを占めています.近年では若手日本人研究者の活躍が目覚ましく,世界をリードする多くの研究が展開されています.こうした流れをさらに加速し,若手水泳研究者への支援,研究者ネットワークづくりなどが当学会に望まれる活動であろうと思います.そのネットワークがさらに水泳研究に興味を抱く様々な立場の人たちが加わることになると信じています.突き抜けた水泳研究者を生み出す土壌づくりを目指し会長として舵を取ろうと考えています.
皆様方のご支援とご協力を今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます.